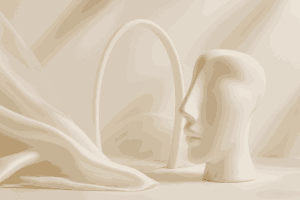ふと鏡を見たとき、以前より顔が疲れて見えたり、フェイスラインがぼやけてきたと感じることはありませんか?それは「顔のたるみ」が原因かもしれません。
顔のたるみは年齢を重ねることで誰にでも起こりうる悩みですが、実はたるみやすい人にはいくつかの特徴があります。
この記事では、顔がたるみやすい人の特徴や主な原因を詳しく解説し、日常生活でできる予防策から美容クリニックでの効果的な対策まで幅広くご紹介します。
ご自身の状態を理解し、適切なケアを始めるための一歩として、ぜひお役立てください。
医学博士
2014年 日本形成外科学会 専門医取得
日本美容外科学会 会員
【略歴】
獨協医科大学医学部卒業後、岩手医科大学形成外科学講座入局。岩手医科大学大学院卒業博士号取得、2014年に日本形成外科学会専門医取得。大手美容クリニックの院長を経て2017年より百人町アルファクリニックの院長を務める。
百人町アルファクリニックでは、糸を使った切らないリフトアップから、切開部分が目立たないフェイスリフトまで患者様に適した方法をご提案していますが、若返り手術は決して急ぐ必要はありません。
一人ひとりの皮下組織や表情筋の状態に合わせた方法を探し「安全性」と「自然な仕上がり」を第一に心がけているため、画一的な手術をすぐにはいどうぞ、と勧めることはしていません。
毎回手術前の診断と計画立案に時間をかけすぎるため、とにかく安く、早くこの施術をして欲しいという方には適したクリニックではありません。それでも、リフトアップの施術を年間300件行っている実績から、患者様同士の口コミや他のドクターからのご紹介を通じ、全国から多くの患者様に当院を選んでいただいています。
このサイトでは、フェイスリフトやたるみに関する情報を詳しく掲載しています。どうか焦らず、十分に勉強した上で、ご自身に合ったクリニックをお選びください。もちろん、ご質問やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
そのお悩み、年齢だけのせいではありません 顔のたるみと向き合うために
「最近、顔がたるんできた気がする…」多くの方が抱えるこの悩み。単に年齢を重ねたからと諦めていませんか?実は、たるみの背景には様々な要因が隠れており、それらを理解することが改善への第一歩です。
年齢だけのせい?たるみのサインを見逃さないで
顔のたるみは加齢だけが原因ではありません。生活習慣や環境要因も大きく関わっています。初期のサインを見逃さず、早めに対策を始めることが重要です。
例えば、以前よりほうれい線が目立つようになった、口角が下がってきた、フェイスラインがぼやけてきたなどは、たるみが進行しているサインかもしれません。
変化に気づいたら、一度立ち止まって原因を探ってみましょう。
「まだ大丈夫」が危険信号?セルフチェックリスト
自分では気づきにくい初期のたるみも存在します。「まだ大丈夫」と思っていても、実はたるみが進行している可能性も。
以下のリストでご自身の状態を客観的にチェックしてみましょう。
たるみ危険度セルフチェック
| チェック項目 | 当てはまる場合の注意点 | 考えられる主な原因 |
|---|---|---|
| 朝と夕方で顔の印象が違う | 夕方になると疲れ顔に見えやすい | むくみ、血行不良、筋力低下 |
| ファンデーションが毛穴に落ちやすくなった | 毛穴の開きやたるみが進行している可能性 | コラーゲン減少、皮脂バランスの乱れ |
| 以前よりほうれい線が深くなった気がする | 頬のたるみが進行しているサイン | 表情筋の衰え、皮膚の弾力低下 |
| 下を向くと二重あごになる | フェイスラインのたるみ、脂肪の蓄積 | 姿勢の悪さ、筋力低下 |
これらの項目に複数当てはまる場合は、たるみが進行している可能性があります。早めのケアを検討しましょう。
たるみが心に与える影響とは
顔のたるみは見た目の変化だけでなく、心理的な影響も及ぼすことがあります。老けて見えることへのコンプレックス、自信の喪失、人と会うのが億劫になるなど、精神的な負担を感じる方も少なくありません。
しかし悩みを抱え込まず、正しい知識を得て対策することで前向きな気持ちを取り戻すことができます。
未来の自分のために今できること
たるみの進行を完全に止めることは難しいかもしれませんが、日々の心がけや適切なケアでそのスピードを緩やかにすることは可能です。
食生活の見直し、正しいスキンケア、表情筋トレーニングなど、今日から始められることはたくさんあります。未来の自分が笑顔でいられるように、今できることから始めてみませんか。
顔がたるみやすい人の特徴
顔のたるみは誰にでも起こりうることですが、特にたるみやすい人にはいくつかの共通した特徴が見られます。
ご自身の生活習慣や体質と照らし合わせながら、たるみのリスクを高めていないか確認してみましょう。
生活習慣に潜むたるみの罠
日々の何気ない習慣が、実は顔のたるみを助長していることがあります。
例えば、睡眠不足やストレスの多い生活は肌のターンオーバーを乱し、コラーゲンの生成を妨げます。また、喫煙は活性酸素を増やし、肌の老化を早める大きな原因の一つです。
たるみを招きやすい生活習慣とその影響
| 生活習慣 | 肌への影響 | たるみへの関与 |
|---|---|---|
| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下、ターンオーバーの乱れ | 肌の修復機能が低下し、ハリが失われやすい |
| 慢性的なストレス | 活性酸素の増加、血行不良 | コラーゲン分解促進、肌の栄養不足 |
| 喫煙 | ビタミンC破壊、血管収縮による血行不良 | 肌の老化促進、弾力低下 |
姿勢とたるみの意外な関係
猫背や長時間のスマートフォン使用によるうつむき姿勢は、顔のたるみに深く関係しています。
悪い姿勢は首や肩の筋肉を緊張させ、血行不良を引き起こします。このことにより顔への栄養供給が滞り、皮膚のハリや弾力が失われやすくなります。
また、うつむいた姿勢は重力の影響を受けやすく、フェイスラインのたるみや二重あごを招く原因にもなります。
食生活の乱れが肌に与える影響
偏った食事や栄養不足は、健康な肌を維持するために必要な栄養素が不足し、たるみを引き起こす原因となります。
特に、タンパク質、ビタミンC、ビタミンE、亜鉛などは、コラーゲンの生成や肌の抗酸化作用に重要な役割を果たします。
インスタント食品やファストフードに偏った食事、過度なダイエットは、これらの栄養素の不足を招きやすいので注意が必要です。
遺伝的要因とたるみやすさ
肌質や骨格など、遺伝的な要因もたるみやすさに関係することがあります。
例えば、皮膚が薄く乾燥しやすい肌質の人は、外部からの刺激を受けやすく、たるみやすい傾向があります。また、顔の骨格によっては、特定の部位にたるみが生じやすいこともあります。
遺伝的な要因を完全に変えることはできませんが、自分の肌質や骨格の特徴を理解し、それに合わせたケアを行うことが大切です。
顔のたるみを引き起こす主な原因
顔のたるみは、単一の原因ではなく複数の要因が複雑に絡み合って進行します。たるみを引き起こす代表的な原因について詳しく見ていきましょう。
加齢によるコラーゲン・エラスチンの減少
肌のハリや弾力を支える主要な成分であるコラーゲンとエラスチンは、年齢とともに体内で生成される量が減少し、質も低下します。
これらの線維が減少したり変性したりすると、皮膚の土台が弱くなり、重力に逆らえずに垂れ下がってしまいます。
特に20代後半から徐々に減少し始め、40代以降になるとその影響が顕著に現れやすくなります。
肌の弾力に関わる主要成分
| 成分 | 主な役割 | 加齢による変化 |
|---|---|---|
| コラーゲン | 肌のハリや構造を支える | 量・質の低下、分解の促進 |
| エラスチン | 肌の弾力性を保つ | 変性、断片化 |
| ヒアルロン酸 | 肌の水分を保持する | 生成量の減少 |
紫外線の影響と光老化
紫外線は、肌の老化を促進する最大の外的要因の一つであり、「光老化」と呼ばれます。
紫外線A波(UVA)は肌の奥深く(真皮層)まで到達し、コラーゲンやエラスチンを変性させたり破壊したりします。
紫外線B波(UVB)は主に表皮にダメージを与え、シミやそばかすの原因となるだけでなく、肌の乾燥やバリア機能の低下を引き起こし、間接的にたるみを促進します。
紫外線によるダメージ
- シミ・そばかすの増加
- 深いシワの形成
- 肌の乾燥とゴワつき
- 弾力性の低下
乾燥が招く肌のハリ低下
肌の乾燥はバリア機能の低下を引き起こし、外部からの刺激を受けやすくなるだけでなく、肌表面のキメを乱し小じわの原因となります。
乾燥が進むと肌内部の水分量が減少し、ハリや弾力が失われやすくなります。この状態が続くと、たるみが進行しやすくなるため、日頃からの保湿ケアが非常に重要です。
表情筋の衰えと皮下脂肪の変化
顔には多くの表情筋があり、これらの筋肉が皮膚を支えています。しかし、加齢や無表情でいる時間が長いことなどにより表情筋が衰えると、皮膚や皮下脂肪を支える力が弱まりたるみが生じます。
また、加齢によって皮下脂肪が減少したり、逆に特定の部分に蓄積したり、位置が移動したりすることも顔のたるみや輪郭の変化に影響を与えます。
部位別に見るたるみの特徴と原因
顔のたるみは、現れる部位によって特徴や主な原因が異なります。それぞれの部位の特性を理解し、適切なケアを行うことが大切です。
目の下のたるみ・クマ
目の下の皮膚は非常に薄くデリケートなため、たるみやクマが現れやすい部位です。
主な原因としては、加齢による眼輪筋の衰えや皮膚の弾力低下、眼窩脂肪(がんかしぼう)の突出などが挙げられます。また、血行不良による青クマや、色素沈着による茶クマも、たるんだ印象を強調することがあります。
頬のたるみとほうれい線
頬のたるみは、顔全体の印象を大きく左右します。加齢によるコラーゲンやエラスチンの減少、表情筋の衰え、皮下脂肪の下垂などが主な原因です。
頬がたるむと口角が下がり、ほうれい線(鼻唇溝)が深くなる傾向があります。
このことにより、疲れた印象や老けた印象を与えやすくなります。
頬のたるみと関連する悩み
| 関連する悩み | 主な原因 | 見た目の特徴 |
|---|---|---|
| ほうれい線 | 頬の皮膚・脂肪の下垂 | 鼻の横から口角にかけての溝 |
| ゴルゴライン | 頬中央部の靭帯のゆるみ、脂肪の減少 | 目頭の下から頬の中央を斜めに走る線 |
| マリオネットライン | 口角下の脂肪の下垂、皮膚のたるみ | 口角から顎にかけて伸びる線 |
フェイスラインの崩れと二重あご
フェイスラインのたるみは、顔の輪郭をぼやけさせてシャープな印象を損ないます。
主な原因は皮膚の弾力低下、広頚筋(こうけいきん)という首の前面にある筋肉の衰え、皮下脂肪の蓄積や下垂です。
特に顎下のたるみは二重あごとして現れやすく、体重の増加だけでなく姿勢の悪さや表情筋の衰えも関係しています。
首のたるみとシワ
首は年齢が現れやすい部位の一つで、顔と同様にたるみやシワが生じやすいです。
首の皮膚は薄く、皮脂腺も少ないため乾燥しやすく紫外線対策も怠りがちです。
加齢によるコラーゲン減少や広頚筋の衰え、長年の姿勢の癖などが首の横ジワや縦ジワ、たるみを引き起こします。
日常でできる顔のたるみ予防策
顔のたるみを完全に防ぐことは難しいですが、日々の生活習慣やスキンケアを見直すことで進行を遅らせたり、軽減したりすることは可能です。
ここでは、今日から始められる予防策をご紹介します。
効果的なスキンケアの基本
たるみ予防のスキンケアで最も重要なのは「保湿」と「紫外線対策」です。
肌が乾燥するとバリア機能が低下し、ハリが失われやすくなります。化粧水で水分を補給した後、乳液やクリームでしっかりと蓋をし、水分蒸発を防ぎましょう。
また、紫外線はコラーゲンやエラスチンを破壊し光老化を引き起こす最大の原因です。季節や天候に関わらず、日焼け止めを毎日塗る習慣をつけましょう。
- 十分な保湿(化粧水、美容液、乳液、クリーム)
- 年間を通じた紫外線対策(日焼け止め、帽子、日傘)
- 肌への摩擦を避ける(優しく洗顔、ゴシゴシこすらない)
表情筋を鍛えるエクササイズ
顔の筋肉である表情筋は、意識して動かさないと衰えやすい性質があります。表情筋を鍛えるエクササイズは、皮膚を支える力を高めたるみ予防に繋がります。
ただし、間違った方法で行うとシワの原因になることもあるため、正しい方法で無理のない範囲で行うことが大切です。
簡単な表情筋エクササイズの例
| エクササイズ名 | 鍛えられる部位 | ポイント |
|---|---|---|
| あいうえお体操 | 口周りの筋肉、頬 | 口を大きく動かし、各音をはっきり発音する |
| 舌回し体操 | 舌の筋肉、フェイスライン | 口を閉じたまま、歯茎の外側を舌でゆっくりなぞる |
| 頬の空気ふくらまし | 頬の筋肉 | 左右の頬を交互に、または両頬を同時に数秒間ふくらませる |
エクササイズを行う際は、鏡を見ながら正しい動きを確認し、無理のない範囲で継続することが重要です。
たるみを防ぐ食事と栄養素
健康な肌を保ち、たるみを予防するためにはバランスの取れた食事が基本です。特に、肌のハリや弾力に関わるコラーゲンの生成をサポートする栄養素を積極的に摂取しましょう。
たるみ予防に役立つ主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 皮膚や筋肉の材料となる | 肉類、魚介類、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲン生成を助ける、抗酸化作用 | 果物(柑橘類、イチゴ)、野菜(パプリカ、ブロッコリー) |
| ビタミンA | 皮膚や粘膜の健康維持、ターンオーバー促進 | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |
| ビタミンE | 抗酸化作用、血行促進 | ナッツ類、植物油、アボカド |
| 亜鉛 | タンパク質の合成、細胞分裂の促進 | 牡蠣、レバー、赤身肉 |
これらの栄養素をバランス良く摂取することを心がけ、加工食品や糖質の摂りすぎには注意しましょう。
質の高い睡眠と生活リズム
質の高い睡眠は、肌のターンオーバーを促し、日中に受けたダメージを修復するために非常に重要です。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、コラーゲンの生成や細胞の修復が行われます。
毎日同じ時間に寝起きするなど、規則正しい生活リズムを整えることも、ホルモンバランスを安定させ肌の健康を保つ上で大切です。
美容クリニックでできるたるみ治療
セルフケアだけでは改善が難しい顔のたるみに対して、美容クリニックでは様々な治療法を提供しています。
糸リフト(スレッドリフト)の特徴と効果
糸リフトは、医療用の特殊な糸を皮下に挿入し、たるんだ皮膚を引き上げる治療法です。
使用する糸には、コグ(トゲのようなもの)が付いており、これが皮下組織に引っかかることでリフトアップ効果を発揮します。また、糸が挿入される刺激により、コラーゲンの生成が促進される効果も期待できます。
ダウンタイムが比較的短く、切開を伴わないため手軽に受けやすいたるみ治療として人気があります。
ハイフ(HIFU)治療の仕組みと期待できること
ハイフ(HIFU:高密度焦点式超音波)は、超音波エネルギーを皮膚の深層部(SMAS筋膜など)に集中的に照射し、熱凝固させることで組織を引き締める治療法です。
メスを使わずにリフトアップ効果が期待でき、特にフェイスラインの引き締めや頬のたるみ改善に適しています。
治療直後から効果を感じる方もいますが、コラーゲン生成が促進されることで、数ヶ月かけて徐々に効果が高まることが多いです。
主な美容クリニックのたるみ治療法比較
| 治療法 | 主な作用機序 | 期待できる効果 | ダウンタイム目安 |
|---|---|---|---|
| 糸リフト | 糸による物理的な引き上げ、コラーゲン生成促進 | 頬・フェイスラインのリフトアップ、ハリ改善 | 数日~1週間程度の腫れ・内出血 |
| ハイフ(HIFU) | 超音波によるSMAS筋膜の熱凝固・収縮 | フェイスラインの引き締め、肌のハリ改善 | ほとんどなし~数日の赤み・腫れ |
| 注入治療(ヒアルロン酸など) | ボリューム補充、シワ改善 | ほうれい線・マリオネットラインの改善、輪郭形成 | ほとんどなし~数日の内出血 |
フェイスリフト手術の種類とメリット・デメリット
フェイスリフト手術は、たるんだ皮膚やSMAS筋膜を引き上げ、余分な皮膚を切除することで顔全体のたるみを根本的に改善する治療法です。
効果の持続期間が長く大幅なたるみ改善が期待できますが、他の治療法に比べてダウンタイムが長くなる傾向があります。
手術範囲や切開部位によっていくつかの種類があります。
代表的なフェイスリフト手術の種類
| 手術名(例) | 主な特徴 | 適応となりやすい方 |
|---|---|---|
| ミニリフト | 比較的小さな切開で、主に頬やフェイスライン下部を引き上げる | 軽度~中程度のたるみの方 |
| フルフェイスリフト | 広範囲の切開で、顔全体から首にかけてのたるみを総合的に改善する | 中程度~重度のたるみの方 |
| ネックリフト | 首のたるみやシワを重点的に改善する | 首のたるみが特に気になる方 |
メリットとしては、効果の高さと持続性が挙げられます。
デメリットとしては、切開を伴うため、腫れや内出血などのダウンタイムが他の治療より長く、傷跡が残る可能性があります(通常は目立たない部位に切開します)。
自分に合った治療法の選び方
たるみ治療には様々な選択肢があるため、どの治療法が自分に合っているか迷う方も多いでしょう。治療法を選ぶ際には、以下の点を考慮することが大切です。
- たるみの程度や部位
- 期待する効果と持続期間
- 許容できるダウンタイム
- 予算
最も重要なのは、信頼できる医師に相談し、自分の状態や希望を正確に伝えることです。カウンセリングを十分に活用し、納得のいく治療法を選びましょう。
よくある質問
顔のたるみ治療に関して、患者様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。
- たるみ治療は痛いですか?
-
治療法によって痛みの程度は異なります。糸リフトや注入治療では、局所麻酔や麻酔クリームを使用するため、痛みを最小限に抑えることができます。
ハイフ治療では、チクチクとした熱感や鈍い痛みを感じることがありますが、多くは我慢できる程度です。フェイスリフト手術は静脈麻酔や全身麻酔で行うため、手術中の痛みはありません。
術後は痛み止めを処方しますので、コントロール可能です。痛みに不安がある場合は、遠慮なく医師にご相談ください。
- 治療後のダウンタイムはどのくらいですか?
-
ダウンタイムも治療法によって大きく異なります。ハイフ治療のように、ほとんどダウンタイムがないものから、フェイスリフト手術のように数週間程度の腫れや内出血が見られるものまで様々です。
一般的に、糸リフトでは数日から1週間程度、注入治療では数日程度の内出血や腫れが出ることがあります。
カウンセリング時に、各治療法の詳しいダウンタイムについて説明しますので、ご自身のライフスタイルに合わせて治療計画を立てることが可能です。
治療法別ダウンタイムと費用の目安
治療法 一般的なダウンタイム 費用相場の目安(税込) 糸リフト 数日~1週間(腫れ、内出血) 10万円~50万円程度(本数による) ハイフ(HIFU) ほぼなし~数日(赤み、軽い腫れ) 5万円~30万円程度(照射範囲による) フェイスリフト手術 2週間~1ヶ月(大きな腫れ、内出血) 80万円~200万円以上(手術範囲による) ※費用はあくまで目安であり、クリニックや治療内容によって異なります。正確な費用はカウンセリング時にご確認ください。 - 効果はどのくらい持続しますか?
-
効果の持続期間も治療法や個人差によって異なります。糸リフトの場合、糸の種類にもよりますが、一般的に1年~2年程度です。ハイフ治療は、半年~1年程度の効果持続が期待できますが、定期的に受けることで効果を維持しやすくなります。
フェイスリフト手術は、他の治療法に比べて効果の持続期間が長く、5年~10年以上効果を実感できることが多いですが、老化の進行を完全に止めるものではありません。
適切なアフターケアや生活習慣を心がけることで、効果を長持ちさせることができます。
- 治療費用はどのくらいかかりますか?
-
治療費用は、選択する治療法、治療範囲、使用する薬剤や糸の種類などによって大きく変動します。上記の表にも目安を記載しましたが、これはあくまで一般的な相場です。
当クリニックでは、カウンセリングにて患者様のお悩みやご希望を詳しく伺い、適した治療プランとそれに伴う費用を明確にご提示します。ご予算に関するご相談も承りますので、お気軽にお申し付けください。
参考文献
SAMIZADEH, Souphiyeh. Anatomy and Pathophysiology of Facial Ageing. In: Thread Lifting Techniques for Facial Rejuvenation and Recontouring. Cham: Springer International Publishing, 2024. p. 61-89.
LIU, Xuan-jun; SULTAN, Muhammad Tipu; LI, Guang-shuai. Obesity, glycemic traits, lifestyle factors, and risk of facial aging: a Mendelian randomization study in 423,999 participants. Aesthetic Plastic Surgery, 2024, 48.5: 1005-1015.
SHOME, Debraj, et al. Aging and the Indian face: an analytical study of aging in the Asian Indian face. Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open, 2020, 8.3: e2580.
KNAGGS, Helen. Skin aging in the Asian population. In: Skin aging handbook. William Andrew Publishing, 2009. p. 177-201.
TRIFAN, Daniela Florina, et al. Involvement of vitamin D3 in the aging process according to sex. Cosmetics, 2023, 10.4: 114.
TRIFAN, Daniela Florina, et al. Can vitamin D levels alter the effectiveness of short-term facelift interventions?. In: Healthcare. MDPI, 2023. p. 1490.
FUSANO, Marta, et al. Comparison of microfocused ultrasound with visualization for skin laxity among vegan and omnivore patients. Journal of Cosmetic Dermatology, 2021, 20.9: 2769-2774.
PIWPONG, Ratchanee. Systematic review on anti-aging health care. Asian Health, Science and Technology Reports, 2018, 26.3: 98-112.