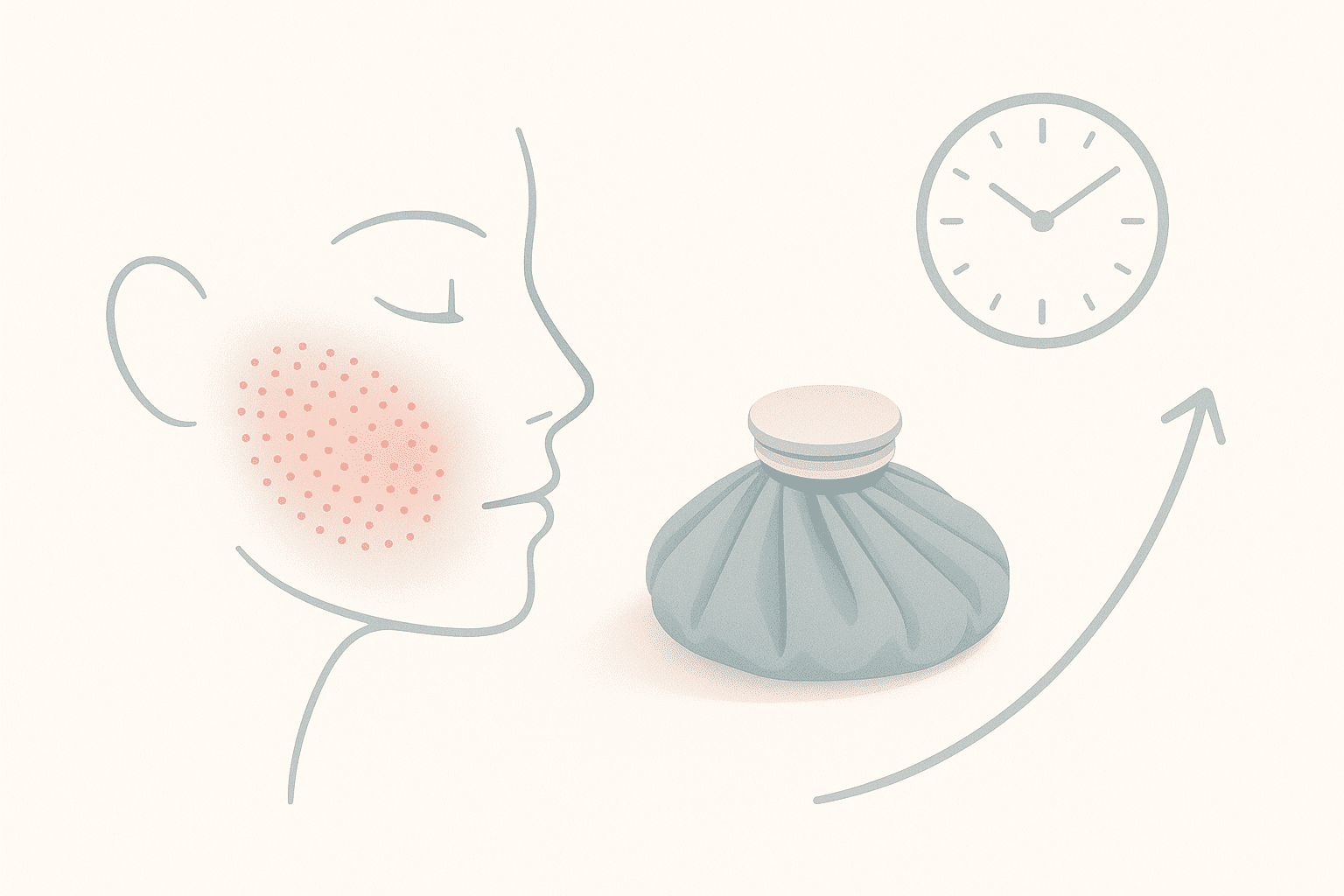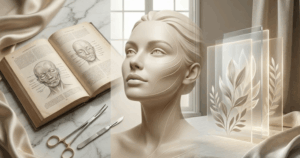フェイスリフト手術を受けたいけれど、術後の「腫れ」や「ダウンタイム」がどれくらい続くのか不安に感じていませんか。
特に仕事や日常生活への影響を考えると、一番つらい時期がいつまで続くのかは、手術を決心する上で大きなポイントになります。
この記事では、フェイスリフト後の腫れのピーク時期やダウンタイムの全容、そしてつらい時期を少しでも快適に、そして賢く乗り切るための具体的な過ごし方を時期を追って詳しく解説します。
医学博士
2014年 日本形成外科学会 専門医取得
日本美容外科学会 会員
【略歴】
獨協医科大学医学部卒業後、岩手医科大学形成外科学講座入局。岩手医科大学大学院卒業博士号取得、2014年に日本形成外科学会専門医取得。大手美容クリニックの院長を経て2017年より百人町アルファクリニックの院長を務める。
百人町アルファクリニックでは、糸を使った切らないリフトアップから、切開部分が目立たないフェイスリフトまで患者様に適した方法をご提案していますが、若返り手術は決して急ぐ必要はありません。
一人ひとりの皮下組織や表情筋の状態に合わせた方法を探し「安全性」と「自然な仕上がり」を第一に心がけているため、画一的な手術をすぐにはいどうぞ、と勧めることはしていません。
毎回手術前の診断と計画立案に時間をかけすぎるため、とにかく安く、早くこの施術をして欲しいという方には適したクリニックではありません。それでも、リフトアップの施術を年間300件行っている実績から、患者様同士の口コミや他のドクターからのご紹介を通じ、全国から多くの患者様に当院を選んでいただいています。
このサイトでは、フェイスリフトやたるみに関する情報を詳しく掲載しています。どうか焦らず、十分に勉強した上で、ご自身に合ったクリニックをお選びください。もちろん、ご質問やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
フェイスリフトの腫れはいつがピーク?ダウンタイムの全体像
フェイスリフト後の腫れのピークは、一般的に手術後2〜3日です。
この腫れは手術を受けたほとんどの方に起こる正常な体の反応であり、ダウンタイムの全体像を把握しておくことで、安心して回復期間を過ごせます。
腫れのピークは術後2〜3日
手術直後よりも、翌日や翌々日に腫れが強くなる傾向があります。
これは手術による組織のダメージに対して、体の治癒反応が活発になるために起こる現象です。リンパ液などが組織の間に溜まることで、顔全体がむくんだように感じます。
この時期は、見た目の上でも感覚的にも最もつらいと感じる方が多いでしょう。
ダウンタイムの一般的な期間
ダウンタイムは、大きく分けて3つの期間に分けられます。
まず、強い腫れや内出血が目立つ「急性期」が約1〜2週間。次に、大きな腫れは引いたものの、まだむくみや違和感が残る「回復期」が約1ヶ月。
そして、細かなむくみも取れてすっきりとし、傷跡も成熟していく「完成期」が3ヶ月から半年ほど続きます。
日常生活に大きな支障がなくなるのは、多くの場合術後2週間程度が目安です。
ダウンタイムの一般的な経過
| 時期 | 主な症状 | 過ごし方のポイント |
|---|---|---|
| 術後1〜3日 | 腫れ・痛みのピーク、内出血 | 安静、アイシング、頭を高くして寝る |
| 術後4日〜1週間 | 強い腫れが引き始める | 抜糸、軽い散歩が可能になる |
| 術後2週間〜1ヶ月 | 大きな腫れや内出血がほぼ消失 | 軽い運動、飲酒が少量可能になる |
なぜ腫れや内出血が起こるのか
フェイスリフト手術では、皮膚の下にあるSMAS(スマス)筋膜という組織を引き上げ、余分な皮膚を切除します。
このとき皮膚や皮下組織を剥がすため、毛細血管が傷つきます。その結果、出血やリンパ液の漏出が起こり、それが「内出血」や「腫れ」として現れます。
体が傷を治そうとする過程で起こる自然な反応であり、手術が成功している証拠とも言えます。
切開範囲と腫れの強さの関係
一般的に、切開範囲が広く剥離する範囲が大きい手術ほど、腫れや内出血は強く出る傾向があります。
こめかみから耳の前、耳の後ろまで大きく切開するフルフェイスリフトは、ミニリフトや部分的なリフトに比べてダウンタイムが長くなる可能性があります。
カウンセリングの際に、ご自身の希望するリフトアップ効果と、許容できるダウンタイムのバランスについて医師としっかり相談することが重要です。
【時期別】ダウンタイム中の具体的な過ごし方
ダウンタイム中は術後3日目までを安静期間とし、その後は徐々に活動レベルを上げていくことが基本的な過ごし方です。
時期ごとに適切なケアを行うことで回復を早め、体への負担を軽減できます。
術後当日〜3日目(ピーク期)の過ごし方
この時期は、とにかく安静第一です。
腫れと痛みが最も強く出るため、無理は禁物。クリニックの指示に従い、処方された痛み止めや抗生剤をきちんと服用しましょう。
体を動かすのはトイレや食事など、必要最低限にとどめます。
寝るときは、枕を2〜3個重ねて頭を心臓より高い位置に保つと、顔に余分な水分が溜まりにくくなり腫れの軽減に役立ちます。
術後4日目〜1週間(回復初期)の過ごし方
ピークを過ぎると、日に日に腫れが引いていくのが実感できるでしょう。痛みも和らぎ、少しずつ動けるようになります。
ただし、まだ油断はできません。血行が良くなりすぎると腫れがぶり返す可能性があるため、長時間の入浴や激しい運動は避けてください。
シャワーは可能になることが多いですが、傷口を濡らさないように注意が必要です。
近所を軽く散歩する程度であれば気分転換にもなり、血行促進にもつながるためおすすめです。
時期別活動レベルの目安
| 時期 | 活動レベル | 注意点 |
|---|---|---|
| 〜3日目 | 安静 | 無理に動かない |
| 〜1週間 | 軽い散歩 | 長時間の外出は避ける |
| 〜1ヶ月 | デスクワーク、軽い運動 | 激しい運動はまだ控える |
術後2週間〜1ヶ月(安定期)の過ごし方
この頃になると大きな腫れや内出血はほとんど目立たなくなり、多くの人が仕事や社会生活に復帰します。
まだ顔に多少のむくみや、皮膚のつっぱり感、感覚の鈍さが残っている場合がありますが、これらも時間とともに改善します。
軽い運動やストレッチも可能になりますが、顔に強い圧力がかかるような運動は避けましょう。
飲酒も少量からなら可能になることが多いですが、飲み過ぎはむくみの原因になるため注意が必要です。
術後1ヶ月以降(完成期)の注意点
術後1ヶ月を過ぎると見た目の変化はかなり落ち着き、手術の効果を実感できるようになりますが、内部組織の回復はまだ続いています。
傷跡は赤みが残っている時期ですが、徐々に白く、目立たなくなっていきます。
この時期からはほとんどの日常生活の制限がなくなりますが、顔のマッサージなど、傷口に強い刺激を与える行為は、術後3ヶ月〜半年程度は避けるのが賢明です。
最終的な仕上がりまで、焦らず見守りましょう。
腫れを早く引かせるためのセルフケア術
腫れを早く引かせるには、術後3日間の徹底したアイシング、頭を高くして寝ること、そして塩分を控えた食事が特に有効です。
セルフケアを正しく行うことでダウンタイムを短縮し、快適に過ごせます。
正しいアイシングの方法と注意点
術後のアイシングは、血管を収縮させて炎症を抑え、腫れや痛みを軽減するのに有効です。腫れのピークである術後72時間(3日間)は積極的に行いましょう。
保冷剤や氷嚢をタオルで包み、1回15〜20分程度、腫れている部分やその周辺を優しく冷やします。
冷やしすぎは凍傷のリスクがあるため、直接肌に当てたり、長時間連続して行ったりするのは避けてください。
アイシングのポイント
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 時間 | 1回15〜20分 | 長時間連続は避ける |
| 頻度 | 1〜2時間おき | 痛みを感じたら中断する |
| 方法 | タオルで包んで優しく当てる | 直接肌に当てない |
頭を高くして寝る工夫
睡眠中に頭の位置を心臓より高く保つことで、重力の助けを借りて顔周りの余分な水分や血液が下がりやすくなります。
この工夫によって、朝起きたときの腫れを軽減できます。
普段使っている枕の上に、もう一つ枕やクッションを重ねたり、リクライニングチェアで休んだりするのも良い方法です。
うつ伏せや横向きで寝ると顔の片側に圧力がかかり、腫れが偏ってしまう可能性があるので、できるだけ仰向けで寝ることを心がけましょう。
食事で気をつけるべきこと
ダウンタイム中の食事は、回復を早める上で意外と重要です。
塩分の多い食事は、体内に水分を溜め込み、むくみや腫れを悪化させる原因になります。加工食品や外食は塩分が多くなりがちなので、できるだけ自炊を心がけ、薄味の和食などを中心にすると良いでしょう。
また、カボチャやスイカ、きゅうりなどのカリウムを多く含む食材は、余分な塩分を体外に排出するのを助けてくれます。
ダウンタイム中に摂取したい栄養素
| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| カリウム | 余分な塩分の排出を助ける | カボチャ、アボカド、バナナ |
| タンパク質 | 組織の修復を助ける | 肉、魚、大豆製品、卵 |
| ビタミンC | コラーゲン生成を助ける | パプリカ、ブロッコリー、果物 |
軽い運動はいつから可能か
術後、安静にしすぎるとかえって血流が悪くなり、回復が遅れることもあります。
抜糸が終わる術後1週間頃から、ウォーキングなどの軽い有酸素運動を始めると、全身の血行が促進され、腫れの早期改善につながります。
ただし、息が上がるような激しい運動や、顔に力が入る筋力トレーニングは、血圧を上昇させて腫れを悪化させる可能性があるため術後1ヶ月程度は控えるのが無難です。
医師の指示に従い、無理のない範囲で体を動かしましょう。
ダウンタイム中の精神的なつらさと乗り越え方
ダウンタイム中の精神的なつらさは「腫れは一時的なもの」と理解し、回復過程の一部だと受け入れることで乗り越えられます。
不安な気持ちは誰にでも起こる自然な感情であり、一人で抱え込まずに信頼できる人やクリニックに相談することが大切です。
見た目の変化に対する精神的な落ち込み
手術後の腫れた顔は、理想の姿とはほど遠いものです。腫れのピーク時には、顔がパンパンに腫れあがり、内出血で青紫色になることもあります。
この見た目の変化にショックを受け、気分が落ち込んでしまうのは自然なことです。「失敗したのかもしれない」というネガティブな感情が湧き上がることもあるでしょう。
しかし、これは一時的な状態であり、回復過程の一部であることを忘れないでください。
精神的な落ち込みへの対処法
| 悩み | 対処法の例 | 心の持ちよう |
|---|---|---|
| 鏡を見るのがつらい | 好きな音楽を聴く、趣味に没頭する | 今は回復に専念する時期と割り切る |
| 本当に治るか不安 | 手術前の写真を見て理想を再確認する | 回復の過程であることを信じる |
| 孤独を感じる | 信頼できる家族や友人に話を聞いてもらう | 一人で抱え込まない |
周囲の視線が気になる時の心の持ちよう
ダウンタイム中は、どうしても他人の目が気になってしまうものです。
「何か言われるのではないか」「手術したことがバレてしまうのではないか」と不安になり、人との交流を避けたくなってしまうかもしれません。
しかし、自分が思うほど他人はあなたのことを気にしていない場合が多いものです。
帽子やメガネ、マスクなどを活用して、物理的に顔をカバーするのも有効な手段です。
また、正直に話せる親しい友人や家族には、事前に事情を伝えておくと余計な気を遣わずに済み、精神的な負担を軽くできます。
食事や会話のしづらさへの対策
手術後は、口周りの腫れや皮膚のつっぱり感で、食事がしにくかったり、口が開きにくくて会話がしづらかったりすることがあります。
このような日常動作の不便さが、ストレスにつながることも少なくありません。
食事は、硬いものや大きく口を開ける必要があるものを避け、おかゆやスープ、ゼリーなど、柔らかく食べやすいものを用意しておくと良いでしょう。
会話がしづらい時期は無理に話そうとせず、筆談やメッセージアプリなどを活用するのも一つの手です。
相談相手がいない孤独感の乗り越え方
家族や友人に美容外科手術のことを打ち明けられず、一人でダウンタイムの不安を抱え込んでいる方もいるでしょう。誰にも相談できない状況は、孤独感を深め、精神的なつらさを増幅させます。
そんな時は、遠慮なくクリニックに連絡してください。あなたの不安や疑問に答えるのが、私たちスタッフの役目です。
同じ手術を経験した多くの患者様を見てきているからこそ、的確なアドバイスができます。一人で悩まず、専門家である私たちを頼ってください。
腫れを悪化させるNG行動と生活習慣
ダウンタイム中に腫れを悪化させる主なNG行動は、長時間の入浴、過度な飲酒・喫煙、そして自己判断による顔のマッサージです。
血行を過剰に促進したり、組織に刺激を与えたりする行為は回復を遅らせるため厳禁です。
長時間の入浴やサウナ
体を温める行為は血行を促進しますが、術後のデリケートな時期に行うと必要以上に血流が良くなり、腫れや内出血を悪化させる原因になります。
術後1週間程度は湯船に浸かるのを避け、ぬるめのシャワーで済ませましょう。サウナや岩盤浴など、体を深部から温める行為は、少なくとも術後1ヶ月は控えるのが賢明です。
過度な飲酒と喫煙
アルコールには血管を拡張させ、血流を促進する作用があります。
ダウンタイム中に飲酒をすると腫れが強く出たり、長引いたりする可能性があります。
また、喫煙は血管を収縮させ、血行を悪化させます。傷の治りに必要な酸素や栄養が届きにくくなるため、回復を遅らせる大きな要因となります。
ダウンタイム中は、禁酒・禁煙を徹底することが美しい仕上がりへの近道です。
回復を妨げる生活習慣
- 塩分の多い食事
- 過度な飲酒
- 喫煙
- 睡眠不足
塩分の多い食事
前述の通り、塩分は体内に水分を溜め込み、むくみの原因となります。ラーメンやスナック菓子、漬物など、塩分の多い食品は特に注意が必要です。
ダウンタイム中は素材の味を活かした薄味の食事を心がけ、体の内側から腫れにくい環境を整えましょう。
避けるべき行動とその理由
| NG行動 | 理由 | いつまで避けるか(目安) |
|---|---|---|
| 長時間の入浴・サウナ | 血行促進による腫れの悪化 | 術後1ヶ月 |
| 過度な飲酒 | 血管拡張による腫れの悪化 | 術後1ヶ月 |
| 顔のマッサージ | 組織への刺激、内出血のリスク | 術後3〜6ヶ月 |
顔のマッサージや強い刺激
早くむくみを取りたいからといって、自己判断で顔をマッサージするのは絶対にやめてください。
手術後の組織は非常にデリケートで、強い刺激を与えると再出血を起こしたり、治癒過程にある組織を傷つけたりする恐れがあります。
洗顔やスキンケアの際も、ゴシゴシこすらず、優しく触れるようにしましょう。
エステなどでのフェイシャルトリートメントも、必ず医師の許可を得てから再開してください。
クリニックに相談すべき危険なサイン
ダウンタイム中にクリニックへすぐに相談すべき危険なサインは、我慢できないほどの激しい痛み、日に日に悪化する腫れ、傷口からの異常な出血などです。
合併症の可能性を示すため、自己判断せず速やかに医師の診察を受ける必要があります。
経験したことのない激しい痛み
術後の痛みは、処方された痛み止めでコントロールできる範囲が通常です。
もし、痛み止めを飲んでも全く効かない、日に日に痛みが強くなる、ズキズキとした拍動性の激しい痛みが続くといった場合は、血腫(皮下に血液が溜まること)や感染の可能性があります。
我慢せずに、すぐにクリニックの緊急連絡先に電話してください。
腫れが日に日に悪化する場合
通常、腫れは術後3日目をピークに徐々に引いていきます。
しかし、1週間経っても腫れが全く引かない、むしろどんどん悪化していく、顔の左右で明らかに腫れ方が違うといった場合も、血腫や感染症などの合併症が疑われます。
特に、腫れとともに強い熱感や赤みを伴う場合は注意が必要です。
すぐに相談すべき症状
| 症状 | 考えられる原因 | 対処 |
|---|---|---|
| 激しい痛み | 血腫、感染 | すぐにクリニックへ連絡 |
| 悪化する腫れ・赤み | 血腫、感染 | すぐにクリニックへ連絡 |
| 傷口からの異常な出血 | 縫合不全、血腫 | すぐにクリニックへ連絡 |
傷口からの異常な出血や浸出液
術後、傷口から少量の血液がにじむことはありますが、サラサラとした血液が止まらない、膿のような色のついた液体が出てくるといった場合は異常のサインです。
特に、嫌な臭いを伴う場合は感染の可能性が高いと考えます。
清潔なガーゼで軽く押さえて、速やかに医師の診察を受けてください。
感覚麻痺が長引く、または悪化する
術後、皮膚の感覚が鈍くなる「感覚麻痺」は多くの人に見られる症状です。手術で皮膚の知覚神経が引き伸ばされるために起こり、通常は数ヶ月かけて回復します。
しかし、この感覚麻痺が全く改善しない、むしろ範囲が広がっていく、口が動かしにくいなどの運動麻痺の症状が出てきた場合は神経損傷の可能性も否定できません。
不安な場合は、些細なことでも医師に伝えましょう。
フェイスリフトのダウンタイムに関するよくある質問
フェイスリフトのダウンタイムについて、仕事の休みは1〜2週間、メイクは抜糸翌日から可能になるのが一般的です。多くの患者様が疑問に思う点について、具体的にお答えします。
- 仕事は何日くらい休む必要がありますか?
-
職種によって必要な休暇期間は異なります。デスクワークなど、人とあまり会わない仕事であれば、大きな腫れが引く1週間程度の休みで復帰される方が多いです。
接客業など人前に出る仕事の場合は、内出血などが落ち着く2週間程度の休みがあるとより安心でしょう。
ご自身の仕事内容や、どこまで許容できるかを考慮してスケジュールを立てることが大切です。
- メイクはいつからできますか?
-
メイクは、抜糸の翌日から可能です。ただし、傷口そのものへのメイクは、術後1ヶ月程度は避けてください。ファンデーションなどを塗る際は、傷口を強くこすらないように注意し、クレンジングも優しく行いましょう。
アイメイクやリップなど、傷口から離れた部分のメイクはもう少し早い段階から可能な場合もあります。
- 傷跡は目立ちますか?
-
フェイスリフトの傷跡は、髪の生え際や耳の前、耳の後ろといった目立ちにくい部分に沿って作られます。
術後しばらくは赤みがありますが、3ヶ月から半年、長い方で1年ほどかけて徐々に白く細い線になり、最終的にはほとんど分からなくなります。
傷跡の治り方には個人差がありますが、医師の技術力によっても大きく左右されるため、経験豊富な医師を選ぶことが重要です。
メイクや洗顔開始の目安
項目 開始時期の目安 注意点 洗顔 医師の指示による(通常術後2〜3日) 傷口を濡らさない、こすらない メイク 抜糸の翌日以降 傷口へのメイクは避ける シャワー 医師の指示による(通常術後2〜3日) 顔や傷口を濡らさない - 2回目のフェイスリフトは可能ですか?
-
はい、可能です。フェイスリフトの効果は永久ではありません。加齢によるたるみが再度進行した場合、2回目、3回目の手術を受けることができます。
ただし、前回の癒着など組織の状態を考慮する必要があるため、初回の手術以上に高度な技術が求められます。一般的には、前回の術後5年〜10年程度経過してから検討することが多いです。
参考文献
SANTOSA, Katherine B., et al. Perioperative management of the facelift patient. Clinics in plastic surgery, 2019, 46.4: 625-639.
FANG, Amanda Hua; DE LA TORRE, Jorge. A Systematic Review of Rhytidectomy Complications and Prevention Methods: Evaluating the Trends. Annals of Plastic Surgery, 2025, 94.6S: S502-S516.
LAWRENCE, Anna, et al. Postoperative Edema Following Rhytidectomy: A New System for Quantifying Lymphedema after Facelift. Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine, 2025.
BOTTI, Chiara; BOTTI, Giovanni; PASCALI, Michele. Facial aging surgery: healing time, duration over the years, and the right time to perform a facelift. Aesthetic Surgery Journal, 2021, 41.11: NP1408-NP1420.
ROUTT, Ethan; NAJJAR, Sarah; CIOCON, David H. Complications in Facial Surgery and Correction of Complications: Forehead Lift, Blepharoplasty, Facelift. Procedures in Cosmetic Dermatology Series: Surgical Lifting E-Book, 2023, 183.
AHMAD, Fatima. Aesthetic surgery. Practical Ambulatory Anesthesia, 2015, 146.
ELKOBI, Tal. Surgical procedures in face and neck rejuvenation. 2023. PhD Thesis. University of Zagreb. School of Medicine.