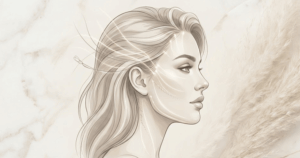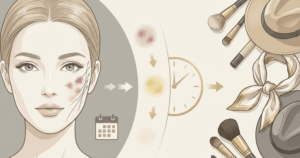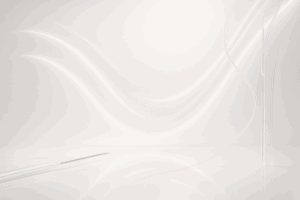顔のたるみやしわが気になり始めたとき、手軽にリフトアップを図りたいという思いから「糸リフト」を検討する方が増えています。切開による大がかりな手術に比べ、ダウンタイムが比較的短い点などが支持を得ている理由の1つといえるでしょう。
しかし、糸リフトにも失敗のリスクがあり、不十分なカウンセリングや誤った施術方法を選ぶと満足できる結果が得られないことがあります。
この記事では糸リフトの失敗例や注意点、リスクを踏まえて予防法を解説し、医師の立場から選び方のポイントをお伝えします。
医学博士
2014年 日本形成外科学会 専門医取得
日本美容外科学会 会員
【略歴】
獨協医科大学医学部卒業後、岩手医科大学形成外科学講座入局。岩手医科大学大学院卒業博士号取得、2014年に日本形成外科学会専門医取得。大手美容クリニックの院長を経て2017年より百人町アルファクリニックの院長を務める。
百人町アルファクリニックでは、糸を使った切らないリフトアップから、切開部分が目立たないフェイスリフトまで患者様に適した方法をご提案していますが、若返り手術は決して急ぐ必要はありません。
一人ひとりの皮下組織や表情筋の状態に合わせた方法を探し「安全性」と「自然な仕上がり」を第一に心がけているため、画一的な手術をすぐにはいどうぞ、と勧めることはしていません。
毎回手術前の診断と計画立案に時間をかけすぎるため、とにかく安く、早くこの施術をして欲しいという方には適したクリニックではありません。それでも、リフトアップの施術を年間300件行っている実績から、患者様同士の口コミや他のドクターからのご紹介を通じ、全国から多くの患者様に当院を選んでいただいています。
このサイトでは、フェイスリフトやたるみに関する情報を詳しく掲載しています。どうか焦らず、十分に勉強した上で、ご自身に合ったクリニックをお選びください。もちろん、ご質問やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
糸リフトとは何か
糸リフトは、細い特殊な糸を皮下組織へ挿入し、たるんだ皮膚を持ち上げることで、若々しいフェイスラインに近づける施術の方法です。従来のフェイスリフトと比べて切開範囲が小さく、入院が必要になるケースが少ないことから注目されています。
ただし、正しい理解がないまま受けると、糸リフトのリスクを軽視してしまう可能性もあるため、まずは基本的なポイントをつかむことが大切です。
糸リフトの基本的な仕組み
糸リフトは、髪の毛ほどの太さの糸を皮膚の下に通し、糸に備わった突起(コグやバーブ)を利用して皮膚を引き上げる技術です。
糸は可溶性の素材である場合が多く、時間の経過とともに体内で吸収されていきます。糸が吸収される過程で、コラーゲン生成が促されてハリが出やすくなるともいわれています。
糸リフト施術の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用する糸の種類 | PDOやPCLなど吸収される素材が一般的 |
| 施術時間 | 30分~60分程度 |
| 麻酔方法 | 局所麻酔または静脈麻酔 |
| 効果の持続期間 | 数カ月~1年半程度(個人差あり) |
糸の種類やデザインはクリニックによって異なり、効果やダウンタイムの長さなども多少変化するため、カウンセリングで納得のいく説明を受けることが重要です。
糸リフトの効果が得られる理由
糸リフトは、糸自体が物理的にたるんだ組織を持ち上げる役割を担います。さらに糸が刺激となって繊維芽細胞が活性化し、コラーゲンの産生が期待できます。そのため、肌質の改善や肌の弾力向上につながることもあるのです。
- 糸の突起が組織を引き上げる
- 挿入時のわずかな傷が修復される過程でコラーゲンが生成される
- 体内吸収型の糸は時間とともに分解され、残らない
しわやたるみが軽度の場合、こうしたメカニズムによって満足できる変化が得られることがあります。ただし、すべての方に理想的な効果が出るわけではない点にも注意が必要です。
糸リフトの施術の流れ
カウンセリングで患者の希望や肌の状態を確認したうえで、デザインを決定します。局所麻酔や静脈麻酔を施し、専用の器具を用いて必要な本数の糸を挿入します。
挿入後は糸の固定や位置の最終確認を行い、施術を終えます。直後は腫れや内出血が見られることもありますが、通常は数日から1週間ほどで落ち着きます。
糸リフトの施術手順
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| カウンセリング | 希望の確認と施術プランの提案 |
| デザイン | 糸を挿入するポイント・本数の決定 |
| 麻酔 | 局所麻酔または静脈麻酔で痛みを軽減 |
| 糸の挿入 | 専用の針やカニューレを使い、糸を所定の位置にセット |
| 仕上げ | 糸の固定具合・左右差を調整して終了 |
従来のフェイスリフトとの相違点
従来のフェイスリフトは切開による施術であり、より大きなたるみの改善が期待できる一方、術後の回復期間が糸リフトよりも長くなることが一般的です。
また糸リフトは皮膚表面への大きな傷を残さないため、ダウンタイムが短い傾向があります。ただし、効果の持続期間や改善の程度は個人差があり、十分な比較検討が必要になります。

糸リフトの失敗例
糸リフトは比較的気軽に受けやすい施術として人気が高まっている一方で、施術後に「失敗では?」と感じる結果となる事例もあります。
ここでは糸リフトの失敗が疑われるいくつかの具体例を取り上げながら、どのような原因が潜んでいるのか考えてみましょう。
過度な引き上げによる不自然さ
過剰に皮膚を引き上げようと糸を強く固定した場合、頬が硬い表情になったり、口元にしわが寄りやすくなったりすることがあります。ナチュラルな仕上がりを求める場合は、強く引きすぎないよう調節する必要があります。
- 無理な引き上げは不自然な顔立ちの原因になる
- 皮膚や筋肉に過剰な負担がかかる
- カウンセリング時に仕上がりイメージをすり合わせることが重要
強く引き上げるほど若返り効果が大きいと思われがちですが、過度な引き上げは顔立ちのバランスを崩す要因になりかねません。
無理な引き上げによる影響
| 症状 | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 不自然な表情 | 糸を強く固定しすぎた | 軽度の再調整または経過観察 |
| 口元・頬のしわ | 笑顔時や動作時の皮膚の引きつり | 糸のテンションを適切に調整 |
| 継続的な痛み | 組織への過度な負荷 | 糸の一部除去や局所処置 |
挿入位置のズレによる左右差
糸の挿入位置が適切でない場合、施術後に左右差が気になることがあります。
顔は本来左右で微妙な差があり、それを考慮せずにまったく同じ位置に挿入すると結果として左右差が大きく目立ってしまう場合があります。
左右差を減らすための工夫
顔の骨格や皮膚の厚みは左右で異なります。術者はこうした個人差を考慮しながらデザインを決め、糸を挿入する深さや角度を微調整します。
カウンセリングではあらかじめ顔の左右差について把握し、左右差がどの程度改善できそうかを確認することが大切です。
糸の露出や感染リスク
糸が皮膚の表面に浮き出てしまったり、糸の先端が飛び出してしまうケースがあります。過去には、皮膚を貫通して糸が見えてしまったという失敗談もあります。
また、施術に伴う創部が化膿して感染が生じることもあり、最悪の場合は糸を抜去しなければならなくなることもあります。
- 皮膚表面への糸の飛び出し
- 細菌感染による腫れや痛み
- 化膿が進むと糸の除去が必要になる場合あり
こうしたトラブルは施術の技術だけでなく、術後のケアの仕方や衛生管理などの要素も絡んできます。
糸露出や感染に関する注意点
| 状態 | 具体的な例 | 対応策 |
|---|---|---|
| 糸の露出 | 皮膚の下から糸が透けたり先端が突き出たりする | 糸の除去または再固定 |
| 感染 | 赤み・熱感・痛み・排膿などが生じる | 抗生剤投与、場合によっては糸の抜去 |
| 炎症後の瘢痕 | 感染が進行し組織が損傷を受ける | 適切なアフターケアと瘢痕治療の検討 |
カウンセリング不足が招く問題
糸リフトの失敗例の多くは、事前のカウンセリングが不十分だったケースと関係があります。
肌状態や目指すイメージ、ライフスタイルなどを十分に反映しないまま施術に臨むと、思ったような仕上がりにならないばかりか、トラブルの予防策も立てにくくなります。
糸リフトに伴うリスクと副作用
糸リフトには「糸リフトの失敗」という結果につながる可能性だけでなく、軽度から重度までさまざまなリスクや副作用が伴います。ここでは腫れや内出血など、施術を行うことで起こる可能性のある具体的な事象を取り上げます。
腫れや内出血の原因
施術で皮膚や血管を刺激するため、腫れや内出血が起こることがあります。これは程度の差こそあれ、多くの患者が経験する一般的な症状です。
腫れは数日でおさまるケースが多いですが、内出血が大きい場合は、治まるのに1~2週間かかることもあります。
- 局所的なダメージにより血管が破れやすい
- 糸を通すときの針やカニューレによる刺激
- 施術後のアイシングや安静が症状緩和につながる
術後の腫れや内出血に影響を与える要素
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 施術時の出血管理 | 血管の損傷を最小限にするテクニックの熟知 |
| 患者の体質 | 血液凝固に影響する薬やサプリの服用状況 |
| 術後のケア | アイシングや圧迫などの対処の丁寧さ |
神経や血管への影響
糸リフトは皮下組織に糸を挿入する施術なので、神経や血管を傷つける危険を完全に排除することはできません。
万が一、大きな血管や主要な神経に糸が干渉してしまうと、しびれや痛み、血行障害などの症状が出ることがあります。ただし、医師が適切な知識をもって解剖学的構造を把握したうえで施術すれば大きなリスクは低減できます。
アレルギー反応の可能性
糸リフトで使用する糸は体内で吸収される素材が主流ですが、人によっては素材に対するアレルギー反応が出ることがあります。
発疹やかゆみ、熱感などが起こった場合はすぐに医療機関へ相談し、必要に応じて糸の抜去や薬物治療を行うことになります。
- 糸の素材(PDO、PCLなど)に対するアレルギー
- 挿入箇所の赤みやかゆみ、ブツブツした発疹
- 悪化すると広範囲に症状が及ぶこともある
術後のダウンタイムの長期化
糸リフトはダウンタイムが比較的短いといわれますが、人によっては回復に時間がかかることもあります。
腫れや痛み、内出血が長期化すれば外出や仕事に支障が出ることがあるため、施術時期を選ぶ際には余裕を持つことが大切です。
術後のダウンタイムを長引かせる要因
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 体質や年齢 | 回復力が低下している場合は腫れや痛みが長引くことがある |
| 糸の本数や挿入の範囲 | 広範囲に施術した場合はそれだけダメージも大きくなる |
| 運動や飲酒、喫煙などの生活習慣 | 術後すぐの激しい運動やアルコール摂取は回復を遅らせる可能性がある |
失敗を防ぐための事前準備
糸リフトのリスクを最小限に抑え、失敗を防ぐためには、施術前の準備やチェックが非常に大切になります。
ここでは主にカウンセリングや検査、そして普段の生活習慣の見直しなどについて取り上げます。
施術前のカウンセリングで伝えるべきこと
医師がカウンセリングで一番知りたいのは「どのような部分をどれくらい改善したいのか」という具体的な希望です。
加えて、既往歴や現在の体調、皮膚の状態やアレルギーの有無などを詳しく伝えることで、より安全な施術計画の立案につながります。
カウンセリング時に伝える情報
- 希望するフェイスラインのイメージ
- これまでの美容医療歴や手術歴
- 皮膚トラブルやアレルギーの経験
- 持病や常用薬の有無
医師に情報をしっかり伝えることで、糸リフトが自分に合っているかどうかも客観的に判断してもらえます。
カウンセリング時のチェック項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 具体的な希望 | 「頬のたるみを引き上げたい」「フェイスラインをすっきり見せたい」など |
| 既往歴・施術歴 | 過去に受けた施術や手術、後遺症・トラブルの有無 |
| 体質・アレルギー | 金属アレルギーや薬剤アレルギー、皮膚病変の有無 |
| 生活習慣 | 喫煙や飲酒、食習慣や睡眠リズムなど |
検査や体調管理の重要性
必要に応じて血液検査などを行うことで、施術当日の体調を把握し、出血リスクや回復力を予測しやすくなります。
また、風邪気味や生理周期などによって施術のタイミングを調整したほうがよい場合もあります。万全の体調で臨むことが良い仕上がりにつながります。
糸選びと施術デザイン
糸リフトには多種多様な素材や形状の糸が存在します。PDOやPCLといった素材、コグの有無や形状の違いによっても、得られる効果や持続期間は変わります。
カウンセリングで医師が選ぶ糸と施術デザインがどのような理由で提案されるのかを知り、理解・納得したうえで施術を受けることが大切です。
よく使用される糸の種類
- PDO(ポリジオキサノン):比較的扱いやすく吸収が早い
- PLLA(ポリ-L-乳酸):体内吸収がやや遅く、持続期間が長め
- PCL(ポリカプロラクトン):柔軟性があり、吸収が緩やか
術前に気をつけたい生活習慣
施術前後は体調を整えることが肝心です。十分な睡眠とバランスの良い食事、適度な運動が回復力を高めます。
喫煙者は術後の傷の治りが遅くなる傾向があるため、可能な限り本数を減らすか禁煙を検討してください。また、過度な飲酒も体への負担につながります。
- 喫煙は血行不良を招き、回復を遅らせる
- 飲酒は浮腫みや出血リスクを高める
- 睡眠不足や偏った食事は肌トラブルの原因になる
施術後の経過と注意点
施術後は体が回復しようとする時期でもあり、糸リフトの効果をより安定させるための行動がポイントとなります。ここではダウンタイム中の過ごし方や腫れ・痛みへの対処、そしてトラブルが起きた場合の対処法について述べます。
ダウンタイムを軽減する過ごし方
糸リフトは傷口が小さいため、ダウンタイムが短いといわれますが、個人差があります。できるだけ体を休め、患部への刺激を最小限に抑えることで腫れや痛みを早く鎮めることが期待できます。
ダウンタイムを軽減する工夫
| 工夫 | 方法 |
|---|---|
| 頭を高めにして寝る | 枕を2つ重ねるなどして血流をコントロール |
| 冷却 | 冷やしすぎに注意しながらアイシング |
| 入浴や運動の制限 | 施術直後は軽めのシャワー程度に留める |
| メイクの工夫 | 傷口に触れないように優しく行う |
腫れや痛みへの対処方法
施術当日から数日は腫れや痛みが出ることがあり、あまりに強い場合はクリニックへ相談することが望ましいです。冷却や痛み止めの服用で対応できる程度であれば、無理のない範囲で様子を見ましょう。
腫れや痛みが長期化するような場合や、痛みが増していく場合には早めの診察が必要です。
- 冷却は短時間を数回にわけて行う
- 痛み止めは医師の指示に従って使用する
- 強い腫れが引かない場合はクリニックへ連絡
施術後のメンテナンスで意識したいこと
施術後は肌が敏感になっているため、乾燥や紫外線ダメージを受けやすい状態です。糸リフトの効果を維持するうえでも、保湿や紫外線対策など、日常的なケアを怠らないようにしましょう。
術後のメンテナンスで大切なポイント
- 保湿対策:乳液やクリームでしっかり保湿
- UV対策:日焼け止めや帽子、日傘の利用
- 適度なマッサージ:強すぎるマッサージは逆効果になることも
- 定期検診:状態の確認や相談のために受診を続ける
トラブルを感じた時の対応策
感染症や糸の露出など明らかなトラブルがあった場合は、自己判断で処置せずにクリニックへ連絡してください。放置すると症状が悪化して治療が長引く可能性があります。
トラブル時の主な症状と対処法を示す表
| 症状 | 対応 |
|---|---|
| 皮膚の強い腫れ・熱感 | すぐにクリニックへ連絡し、指示を仰ぐ |
| 糸の突起・飛び出し | 医師による糸の再固定や一部除去 |
| しこりや硬結感 | 軽度なら様子見だが、持続・拡大する場合は受診が必要 |
糸リフトを成功させる医師選び
糸リフトの結果を左右する大きな要因として、施術を行う医師の技術力とカウンセリング力が挙げられます。ここでは信頼できる医師を見極めるポイントや、糸リフトが上手な医師を探すための具体的な観点を説明します。
信頼できる医師を見極める要素
医師の技術だけに注目しがちですが、実際にはコミュニケーションやアフターサポートの充実度など、総合的に判断することが大切です。
患者の求めるイメージを理解し、それを踏まえたうえで安全かつ的確な施術を提供してくれる医師が望まれます。
- 患者の希望を丁寧にヒアリングする
- メリットだけでなくリスクもきちんと説明する
- 疑問や不安に対して根拠をもって回答してくれる
症例数や実績の確認
糸リフトの施術数が多い医師ほど、さまざまなケースに対応している可能性が高いです。ただし、症例数を誇示するだけではなく、その内容や患者満足度に関する情報も確認するのが望ましいです。
医師選びでチェックしたい項目
| 項目 | 注目する理由 |
|---|---|
| 症例数 | 経験値と豊富な事例への対応力 |
| 学会・認定資格 | 専門性やエビデンスに基づいた施術ができるかどうか |
| 口コミや評判 | 実際の患者の体験談から得られる総合評価 |
カウンセリングにおけるポイント
カウンセリングでは、単に施術の説明だけでなく、患者の悩みや期待を引き出すコミュニケーション能力も求められます。
カウンセリング時間をしっかり確保し、施術の限界や起こりうるトラブルなども含めて率直に伝える医師は信頼度が高いといえるでしょう。
糸リフトが上手な医師を探すための情報収集
クリニックのホームページやSNS、口コミサイトなどを活用して医師の施術実績や学会活動を確認することができます。
実際にカウンセリングに足を運んでみることも大切です。複数の医師と面談し、自分との相性を見極めることで、納得のいく施術を受けやすくなります。
- 公式サイトに施術例やビフォーアフターがあるか
- 学会発表や論文執筆など学術的な活動履歴
- カウンセリング時の対応や説明のわかりやすさ
フェイスリフト手術との比較
たるみの度合いや希望する仕上がりによっては、糸リフトだけでなく切開を含むフェイスリフト手術を検討する場合もあります。
ここでは主に施術効果やダウンタイム、費用などの観点から両者を比較し、将来的な施術プランも視野に入れた考え方を紹介します。
たるみの度合いによる選択
中等度以上のたるみがある方には、切開によるフェイスリフトが望ましい場合があります。一方で、加齢による軽度のたるみやしわであれば、糸リフトで満足できるケースも少なくありません。
医師の診察とカウンセリングで、自分のたるみの程度に応じて選択することが重要です。
たるみの度合いと適する施術例
| たるみレベル | 選択が考えられる施術 |
|---|---|
| 軽度(しわ・ハリ不足) | 糸リフト、ヒアルロン酸注入など |
| 中度(頬・顎下のたるみ) | 糸リフトと切開リフトの併用を検討 |
| 重度(フェイスラインの崩れ) | 切開によるフェイスリフト |
持続期間の違い
一般的に糸リフトの効果は半年から1年程度であり、個人差も大きいです。それに対して切開によるフェイスリフトは、数年単位で効果が続くとされる傾向があります。
短期的に効果を試したいなら糸リフト、長期的なしっかりしたリフト効果を目指すなら切開リフト、といった選び方も考えられます。
ダウンタイムや費用面での考え方
切開リフトは糸リフトに比べて手術が大がかりになるため、ダウンタイムや費用面で糸リフトよりも負担が大きくなる傾向があります。
ただし、長期的な効果を求める場合は、複数回の糸リフトより切開リフトのほうが結果的にコストパフォーマンスが高くなるケースもあります。
- 切開リフト:手術費用や入院費などが高額になりやすい
- 糸リフト:繰り返し施術することで総費用が増える可能性あり
- 長期的な見通しと今の予算の両面から検討することが必要
将来的な施術プランの見通し
30代~40代の比較的若い年齢で軽度のたるみが気になる場合には、糸リフトで徐々に改善を図りながら、将来的に切開リフトを視野に入れる方もいます。
一度に大きな施術をするのではなく、年齢や生活状況に合わせてプランを組み立てると、リスク分散にもつながります。
糸リフトで理想のフェイスラインを目指すには
施術そのものの技術だけでなく、自分の中での目標設定やクリニックとの信頼関係も結果に大きく影響します。最後に、糸リフトによるフェイスライン改善を成功させるために心がけたいポイントをまとめます。
施術の目的を明確にする
「若々しい印象にしたい」「顎のラインをシャープに見せたい」「フェイスラインのもたつきを少し引き締めたい」など、どの部分をどれだけ変えたいのかを具体的にイメージすることが重要です。
目的が曖昧だと、医師とのイメージ共有が難しくなり、満足度にも影響します。
目的を具体化するためのヒント
| 目的例 | 施術方針とのつながり |
|---|---|
| 頬のハリを取り戻したい | 糸を頬骨周辺に配置してリフトアップ |
| 顎下のたるみを解消したい | 顎下ラインに重点的に糸を入れ、フェイスラインをすっきり |
| ほうれい線を目立たなくしたい | 糸リフト+ヒアルロン酸などの組み合わせ |
カウンセリングから得られる安心
カウンセリングを丁寧に行うクリニックほど、施術後の結果をイメージしやすくなり、万が一のトラブルにも迅速に対応してくれます。
糸リフトのリスクや失敗例についても一通り説明を受けておくことで、安心感を得られるでしょう。
- カウンセリングの時間を十分に確保しているか
- 医師やスタッフの対応が丁寧か
- リスク説明とメリット説明のバランス
術後ケアを継続する意義
施術後は数日から数週間程度のダウンタイムだけでなく、その後も定期的にクリニックへ通うことで状態をチェックできます。
特に初回の糸リフトの場合、経過観察や軽微な調整を行うことで仕上がりを整えやすくなります。
- 施術後の検診は仕上がりを左右する大切なプロセス
- 小さな不安や疑問を早めに解決することで大きなトラブルを防げる
- クリニックによっては施術後〇カ月無料検診などのサポート体制あり
クリニックとの長期的な関係づくり
糸リフトの効果は永遠に続くわけではなく、加齢による変化は避けられません。
だからこそ、信頼できるクリニックや医師と長期的に関係を築いておくことで、必要に応じて別の施術の提案を受けたり、メンテナンスの頻度を調整したりしやすくなります。
- 定期的に肌状態をチェックしてもらう
- 他の美容施術と組み合わせながら総合的にエイジングケアを行う
- 糸リフトでの失敗を回避しやすいバックアップ体制が整う
「糸リフトが上手な先生に見てもらいたい」と考えている方は、こうしたクリニックとの信頼関係も重視して探してみることをおすすめします。
参考文献
NIU, Zehao, et al. A meta-analysis and systematic review of the incidences of complications following facial thread-lifting. Aesthetic plastic surgery, 2021, 45: 2148-2158.
LI, Yi-Lin, et al. Facial thread lifting complications in China: analysis and treatment. Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open, 2021, 9.9: e3820.
WANG, Cheng‐Kun. Complications of thread lift about skin dimpling and thread extrusion. Dermatologic Therapy, 2020, 33.4.
YEO, Seung Hun; LEE, Young Bae; HAN, Dong Gil. Early Complications from Absorbable Anchoring Suture Following Thread-Lift for Facial Rejuvenation. Archives of Aesthetic Plastic Surgery, 2017, 23.1: 11-16.
GÜLBITTI, Haydar Aslan, et al. Thread-lift sutures: still in the lift? A systematic review of the literature. Plastic and reconstructive surgery, 2018, 141.3: 341e-347e.
YONGTRAKUL, Panprapa, et al. Thread lift: classification, technique, and how to approach to the patient. World Acad Sci Eng Technol, 2016, 10.10: 558-66.
REZAEE KHIABANLOO, Samad; NABIE, Reza; AALIPOUR, Ezatollah. Outcomes in thread lift for face, neck, and nose; A prospective chart review study with APTOS. Journal of Cosmetic Dermatology, 2020, 19.11: 2867-2876.
REZAEE KHIABANLOO, Samad, et al. Innovative techniques for thread lifting of face and neck. Journal of cosmetic dermatology, 2019, 18.6: 1846-1855.
SARIGUL GUDUK, Sukran; KARACA, Nezih. Safety and complications of absorbable threads made of poly‐L‐lactic acid and poly lactide/glycolide: experience with 148 consecutive patients. Journal of Cosmetic Dermatology, 2018, 17.6: 1189-1193.